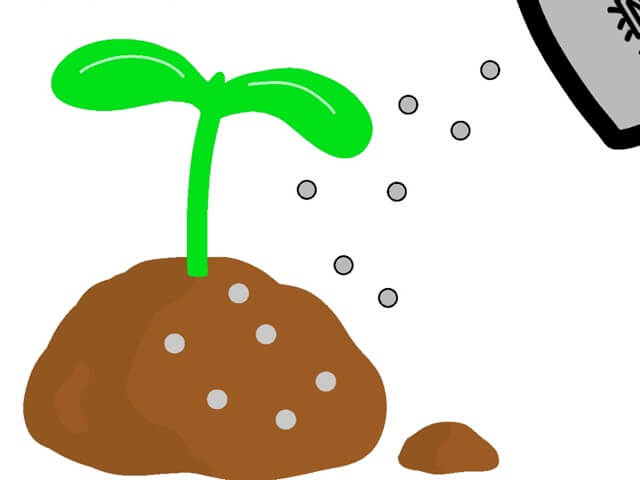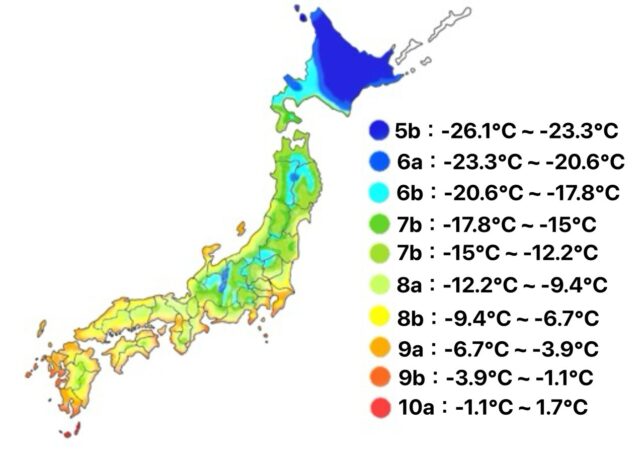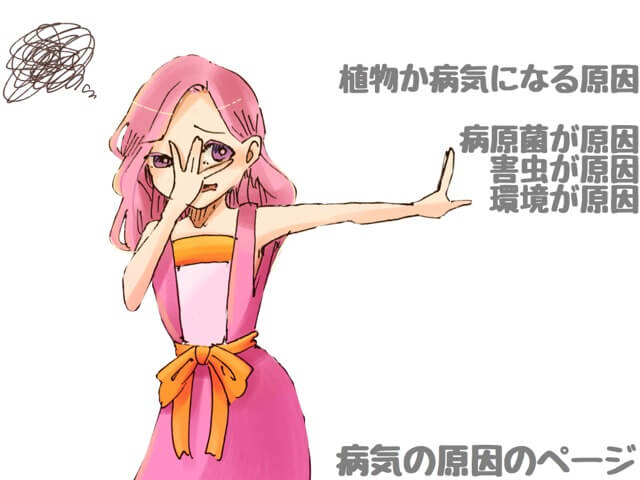ツタ属は約14種があり、園芸でも様々な種と品種が親しまれています。このページでは3種類の原種と、いくつかの園芸品種を紹介しています。
上記の他にも、このページでは育て方や購入する際のリンクも用意しています。よければ、そちらもご活用ください。
■目次
■ツタ属の簡易比較

学名:Parthenocissus quinquefolia
生活形:落葉性ツル性木本
全長:約10~30m
開花:6月~7月
花色:緑色・黄緑色
葉色:緑色・桃色(品種)・黄色(品種)・橙色(紅葉)・赤色(紅葉)・紫色(紅葉)
生育型:ツル型
備考:この植物の魅力は、壁面などの大きな構造物を簡単に覆えるほどのツルの長さと登攀能力や、5枚の小葉で構成されるお洒落な葉の形にあります。このツルは、全長30mまで達することがあり、巻きひげの先の吸盤で他物に付着し、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、園芸では壁面緑化のツル植物として栽培されています。またツタは落葉性で冬に葉が落ちる性質があるため、春から夏は青々とした元気な葉を楽しみ、秋は真っ赤に色付く紅葉を鑑賞し、冬は壁面を這うツルが作り出す独特なテクスチャーを楽しみ、季節の移り変わりを感じることが出来ます。葉は掌状複葉で小葉が5枚あり、分裂葉で裂片が3枚ある日本のツタ(Parthenocissus tricuspidata)と区別が出来ます。また園芸品種の中には葉の色が黄色や桃色をしているものもあるため、カラーリーフとしても楽しめるでしょう。本種は耐寒性・耐暑性が高く、栄養の乏しい土壌や乾燥した土壌にも適応し、日向から明るい日陰までと幅広い環境で育てられ、基本的に強健です。そのため、栽培は簡単ですが、一方でツルが旺盛に伸びて定期的に剪定をしないと制御が難しくなることも多く、吸盤が付着した構造物を破損することもあるため管理には注意が必要です。また茎・葉・果実にシュウ酸カルシウム結晶が大量に含有しているため、有毒で食べられないことはもちろん、樹液への接触も肌が炎症を起こすため扱いに十分な注意が必要となります。

学名:Parthenocissus tricuspidata
生活形:落葉性ツル性木本
全長:約10~30m
開花:6月~7月
花色:緑色・黄緑色
葉色:緑色・黄色(品種)・橙色(紅葉)・赤色(紅葉)・紫色(紅葉)
生育型:ツル型
備考:この植物の魅力は、壁面などの大きな構造物を簡単に覆えるほどのツルの長さと登攀能力にあります。このツルは、全長30mまで達することがあり、巻きひげの先の吸盤で他物に付着し、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、園芸では壁面緑化のツル植物として栽培されています。またツタは落葉性で冬に葉が落ちる性質があるため、春から夏は青々とした元気な葉を楽しみ、秋は真っ赤に色付く紅葉を鑑賞し、冬は壁面を這うツルが作り出す独特なテクスチャーを楽しみ、季節の移り変わりを感じることが出来ます。また園芸品種の中には葉の色が黄色や赤色をしているものもあるため、カラーリーフとしても楽しめるでしょう。本種は耐寒性・耐暑性が高く、栄養の乏しい土壌や乾燥した土壌にも適応し、日向から明るい日陰までと幅広い環境で育てられ、基本的に強健です。そのため、栽培は簡単ですが、一方でツルが旺盛に伸びて定期的に剪定をしないと制御が難しくなることも多く、吸盤が付着した構造物を破損することもあるため管理には注意が必要です。

学名:Parthenocissus henryana
生活形:落葉性ツル性木本
全長:約5~10m
開花:6月~7月
花色:緑色・黄緑色
葉色:緑色・鶯色・白色・赤色(紅葉)・橙色(紅葉)・紫色(紅葉)
生育型:ツル型
備考:この植物の魅力は、壁面などの構造物を覆えるほどのツルの長さと登攀能力や、葉脈に明瞭に入る白色の脈斑にあります。このツルは、全長10mまで達することがあり、巻きひげの先の吸盤で他物に付着し、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、園芸では壁面緑化のツル植物として栽培されています。またツタは落葉性で冬に葉が落ちる性質があるため、春から夏は青々とした元気な葉を楽しみ、秋は真っ赤に色付く紅葉を鑑賞し、冬は壁面を這うツルが作り出す独特なテクスチャーを楽しみ、季節の移り変わりを感じることが出来ます。葉は掌状複葉で小葉が基本的に5枚あり、葉色は緑色(鶯色)を基調として白色の脈斑が入るためカラーリーフとして楽しめる点も魅力です。本種は耐寒性・耐暑性が高く、栄養の乏しい土壌や乾燥した土壌にも適応し、日向から明るい日陰までと幅広い環境で育てられ、基本的に強健です。そのため、栽培は簡単ですが、一方でツルが旺盛に伸びて定期的に剪定をしないと制御が難しくなることも多く、吸盤が付着した構造物を破損することもあるため管理には注意が必要です。
■ツタ属の主な種と園芸品種の紹介
●主な原種
アメリカヅタ


アメリカヅタとは!
アメリカヅタ(学名: Parthenocissus quinquefolia)は、別名で「バージニアクリーパー(Virginia creeper)」「ファイブ・リーブ・アイビー(five-leaved ivy)」とも呼ばれるブドウ科ツタ属の落葉性ツル性木本です。
アメリカヅタの原産地はアメリカ合衆国、カナダ、メキシコで、自生地は森林の林床、林縁、岩壁、また人為的攪乱を受けた荒地などで見られます。
アメリカヅタの特徴
- アメリカヅタの魅力:この植物の魅力は、壁面などの大きな構造物を簡単に覆えるほどのツルの長さと登攀能力や、5枚の小葉で構成されるお洒落な葉の形にあります。このツルは、全長30mまで達することがあり、巻きひげの先の吸盤で他物に付着し、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、園芸では壁面緑化のツル植物として栽培されています。またツタは落葉性で冬に葉が落ちる性質があるため、春から夏は青々とした元気な葉を楽しみ、秋は真っ赤に色付く紅葉を鑑賞し、冬は壁面を這うツルが作り出す独特なテクスチャーを楽しみ、季節の移り変わりを感じることが出来ます。葉は掌状複葉で小葉が5枚あり、分裂葉で裂片が3枚ある日本のツタ(Parthenocissus tricuspidata)と区別が出来ます。また園芸品種の中には葉の色が黄色や桃色をしているものもあるため、カラーリーフとしても楽しめるでしょう。本種は耐寒性・耐暑性が高く、栄養の乏しい土壌や乾燥した土壌にも適応し、日向から明るい日陰までと幅広い環境で育てられ、基本的に強健です。そのため、栽培は簡単ですが、一方でツルが旺盛に伸びて定期的に剪定をしないと制御が難しくなることも多く、吸盤が付着した構造物を破損することもあるため管理には注意が必要です。また茎・葉・果実にシュウ酸カルシウム結晶が大量に含有しているため、有毒で食べられないことはもちろん、樹液への接触も肌が炎症を起こすため扱いに十分な注意が必要となります。
- 樹形:生育型はツル型で、茎の種類はツル、ツルの全長は約10~30mに達し、基本的に柔軟で他物がない場合は地表を這い、樹木や岩壁などがある場合は、ツルから発生する巻きひげのうち先端の吸盤を他物に付着させて、自らを他物に固定しながら上へと成長します。
- 葉の特徴:葉は互生で、葉と対生する位置の節から巻きひげをつけます。葉の概形は掌状複葉で、一般的に小葉は5枚ありますが、若い茎では小葉が3枚または稀に7枚あることもあります。葉の色は基本的に緑色で、秋になると赤色または橙色や紫色に紅葉し、冬になると落葉します。また園芸品種の中には黄色や桃色や赤色などの葉色もあるため、品種を選べばカラーリーフとして楽しむ事もできるでしょう。
- 花の特徴:開花時期は初夏から夏、花序は集散花序です。小花は非常に小さく、緑色をしていて、鑑賞価値はほとんどありません。
- ツル植物:アメリカヅタは生育型がツル型で、他物を支えながら成長する植物です。ツルは巻きひげの先端にある吸盤を他物に付着させて、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、ツル植物として仕立て栽培する場合は、樹木に這わせたり、凹凸のある壁面に這わせたり、また資材(ヘゴ支柱・ココスティック・パネル)を準備して、これらに誘引して栽培されます。ただし、吸盤が物体に付着して張り付くため、岩壁や木造などの構造物を劣化させる可能性があります。そのため、十分な計画を立てて栽培しましょう。
- シェードガーデン:アメリカヅタは耐陰性があるため、日向はもちろん、直射日光が当たらない明るい日陰でも栽培が可能です。
- 毒性:アメリカヅタは、茎・葉・果実に有毒成分であるシュウ酸カルシウム結晶が含まれています。シュウ酸カルシウムが含まれる樹液が肌に触れるだけで、炎症や強い痒み等を引き起こす可能性があり、粘膜につくと強い痛みをともないます。また摂取した場合は、直ぐに口内が炎症して荒れたり、嘔吐や下痢を引き起こしたり、胃腸が荒れたりする他、尿路結石を引き起こす原因にもなり、大量に摂取した場合は死に至ることもあります。そのため、取り扱いには十分な注意が必要になり、また子供やペットのいる家庭で、この植物を栽培する際は特に注意が必要となります。万が一、樹液に触れた場合は、直ちに大量の流水で洗い流して下さい。また誤って摂取した場合は、口をよくすすぎ、近くの医療機関を受診するとよいでしょう。
アメリカヅタの園芸品種の紹介
エンゲルマンニー

学名:Parthenocissus quinquefolia ‘engelmannii’
葉の色:緑色・橙色(紅葉)・赤色(紅葉)・紫色(紅葉)
全長:約5~10m
備考:秋の紅葉期にみられる鮮やかな赤色・橙色・紫色に変化する葉色が魅力の品種です。
ミステリーピンク
学名:Parthenocissus quinquefolia ‘mystery pink’
葉の色:緑色・クリーム色・桃色
全長:約5~20m
備考:葉の色は緑色・クリーム色・桃色の3色で、新芽と若葉の色が桃色へと染まり、成熟した葉は緑色とクリーム色の散斑(切斑と星斑)が入ります。そのため、かわいいをテーマにするお庭などによく合う品種です。
ツタ


ツタとは!
ツタ(学名: Parthenocissus tricuspidata)は、別名で「ナツヅタ」「アマヅラ」「モミジヅタ」「ジャパニーズ・アイビー(Japanese ivy)」「ジャパニーズ・クリーパー(Japanese creeper)」「ボストン・アイビー(Boston ivy)」とも呼ばれるブドウ科ツタ属の落葉性ツル性木本です。
ツタの原産地は日本を含む東アジアで、自生地は温帯の森林の林床、林縁、崖地などで見られます。
ツタの特徴
- ツタの魅力:この植物の魅力は、壁面などの大きな構造物を簡単に覆えるほどのツルの長さと登攀能力にあります。このツルは、全長30mまで達することがあり、巻きひげの先の吸盤で他物に付着し、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、園芸では壁面緑化のツル植物として栽培されています。またツタは落葉性で冬に葉が落ちる性質があるため、春から夏は青々とした元気な葉を楽しみ、秋は真っ赤に色付く紅葉を鑑賞し、冬は壁面を這うツルが作り出す独特なテクスチャーを楽しみ、季節の移り変わりを感じることが出来ます。また園芸品種の中には葉の色が黄色や赤色をしているものもあるため、カラーリーフとしても楽しめるでしょう。本種は耐寒性・耐暑性が高く、栄養の乏しい土壌や乾燥した土壌にも適応し、日向から明るい日陰までと幅広い環境で育てられ、基本的に強健です。そのため、栽培は簡単ですが、一方でツルが旺盛に伸びて定期的に剪定をしないと制御が難しくなることも多く、吸盤が付着した構造物を破損することもあるため管理には注意が必要です。
- 樹形:生育型はツル型で、茎の種類はツル、ツルの全長は約10~30mに達し、基本的に柔軟で他物がない場合は地表を這い、樹木や岩壁などがある場合は、ツルから発生する巻きひげのうち先端の吸盤を他物に付着させて、自らを他物に固定しながら上へと成長します。
- 葉の特徴:葉は互生で、葉と対生する位置の節から巻きひげをつけます。葉の概形は異形葉性のため若い茎と成熟した茎で葉の見た目が大きく異なります。若い茎の葉は複葉で概形は3出複葉を呈し、小葉は卵形・楕円形、葉縁部に鋸歯があります。一方で、成熟した茎の葉は単葉で、概形は広卵形・心形をしており、葉縁部が掌状浅裂または掌状中裂し、基本的に先端に鋭形の裂片が3個、稀に5個あります。葉の色は基本的に緑色で、秋になると赤色または橙色や紫色に紅葉し、冬になると落葉します。また園芸品種の中には黄色や赤色などの葉色もあるため、品種を選べばカラーリーフとして楽しむ事もできるでしょう。
- 花の特徴:開花時期は初夏から夏、花序は集散花序です。小花は非常に小さく、緑色をしていて、鑑賞価値はほとんどありません。
- ツル植物:ツタは生育型がツル型で、他物を支えながら成長する植物です。ツルは巻きひげの先端にある吸盤を他物に付着させて、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、ツル植物として仕立て栽培する場合は、樹木に這わせたり、凹凸のある壁面に這わせたり、また資材(ヘゴ支柱・ココスティック・パネル)を準備して、これらに誘引して栽培されます。ただし、吸盤が物体に付着して張り付くため、岩壁や木造などの構造物を劣化させる可能性があります。そのため、十分な計画を立てて栽培しましょう。
- シェードガーデン:ツタは耐陰性があるため、日向はもちろん、直射日光が当たらない明るい日陰でも栽培が可能です。
ツタの園芸品種の紹介
ヘンリーヅタ

ヘンリーヅタとは!
ヘンリーヅタ(学名: Parthenocissus henryana)は、別名で「チャイニーズ バージニアクリーパー(Chinese Virginia creeper)」「シルバー・ヴェイン・クリーパー(silver vein creeper)」とも呼ばれるブドウ科ツタ属の落葉性ツル性木本です。
ヘンリーヅタの原産地は中国で、自生地は標高1500mまでの森林の湿潤な岩場や岩壁などで見られます。
ヘンリーヅタの特徴
- ヘンリーヅタの魅力:この植物の魅力は、壁面などの構造物を覆えるほどのツルの長さと登攀能力や、葉脈に明瞭に入る白色の脈斑にあります。このツルは、全長10mまで達することがあり、巻きひげの先の吸盤で他物に付着し、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、園芸では壁面緑化のツル植物として栽培されています。またツタは落葉性で冬に葉が落ちる性質があるため、春から夏は青々とした元気な葉を楽しみ、秋は真っ赤に色付く紅葉を鑑賞し、冬は壁面を這うツルが作り出す独特なテクスチャーを楽しみ、季節の移り変わりを感じることが出来ます。葉は掌状複葉で小葉が基本的に5枚あり、葉色は緑色(鶯色)を基調として白色の脈斑が入るためカラーリーフとして楽しめる点も魅力です。本種は耐寒性・耐暑性が高く、栄養の乏しい土壌や乾燥した土壌にも適応し、日向から明るい日陰までと幅広い環境で育てられ、基本的に強健です。そのため、栽培は簡単ですが、一方でツルが旺盛に伸びて定期的に剪定をしないと制御が難しくなることも多く、吸盤が付着した構造物を破損することもあるため管理には注意が必要です。
- 樹形:生育型はツル型で、茎の種類はツル、ツルの全長は約5~10mに達し、基本的に柔軟で他物がない場合は地表を這い、樹木や岩壁などがある場合は、ツルから発生する巻きひげのうち先端の吸盤を他物に付着させて、自らを他物に固定しながら上へと成長します。
- 葉の特徴:葉は互生で、葉と対生する位置の節から巻きひげをつけます。葉の概形は掌状複葉で、一般的に小葉は5枚ありますが、稀に小葉が3枚または最大9枚あることもあります。葉の色は緑色または鶯色を基調とし、白色の太い脈斑が入り、秋になると赤色または橙色や紫色に紅葉し、冬になると落葉します。
- 花の特徴:開花時期は初夏から夏、花序は集散花序です。小花は非常に小さく、緑色をしていて、鑑賞価値はほとんどありません。
- ツル植物:ヘンリーヅタは生育型がツル型で、他物を支えながら成長する植物です。ツルは巻きひげの先端にある吸盤を他物に付着させて、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、ツル植物として仕立て栽培する場合は、樹木に這わせたり、凹凸のある壁面に這わせたり、また資材(ヘゴ支柱・ココスティック・パネル)を準備して、これらに誘引して栽培されます。ただし、吸盤が物体に付着して張り付くため、岩壁や木造などの構造物を劣化させる可能性があります。そのため、十分な計画を立てて栽培しましょう。
- シェードガーデン:ヘンリーヅタは耐陰性があるため、日向はもちろん、直射日光が当たらない明るい日陰でも栽培が可能です。
ヘンリーヅタの園芸品種の紹介
●その他の品種
シュガーバイン

育て方・楽天で購入
シュガーバインの学名:学名はClematicissus striata ‘sugarvine’で、または同義語でParthenocissus ‘sugarvine’またはCissus striata ‘sugarvine’やVitis striataとされる品種です。
魅力:シュガーバインの魅力は、生活型がツル型で様々な仕立て方ができる点、葉は掌状複葉になりサイズが小さいため可愛らしさや繊細さを感じさせる点などにあります。
草姿:生育型はツル型で、茎の種類はツル、ツルの全長は約100~500cmに達し、基本的に柔軟で他物がない場合は地表を這い、樹木や岩壁などがある場合は、ツルから発生する巻きひげを他物に絡めて、自らを他物に固定しながら上へと成長します。
葉の特徴:葉は互生で、葉と対生する位置の節から巻きひげをつけます。葉の概形は掌状複葉で小葉は5枚あり小葉は楕円形または倒卵形をしています。葉の色は緑色で秋になると紅葉し、冬になると落葉する。
花の特徴:開花期は夏頃、花序は集散花序です。小花は非常に小さく、緑色をしていて、鑑賞価値はほとんどありません。
ツル植物:シュガーバインは生育型がツル型で、他物を支えながら成長する植物です。ツルは巻きひげを他物に付着させて、自らを固定しながら上へと成長します。そのため、ツル植物として仕立て栽培する場合は、また資材(支柱・トレリス・アーチ等)を準備して、これらに誘引して栽培されます。
枝垂れ植物:シュガーバインは、草姿がツル型で茎は柔軟で壁面から真っ直ぐ下に下垂する性質があります。そのため、ハンギング鉢などに植えると鉢縁から滝のように枝垂れる草姿が鑑賞できたり、またロックガーデンや石垣の側に植えると岩肌を被覆するように枝垂れる草姿が鑑賞できたりします。
シェードガーデン:ヘンリーヅタは耐陰性があるため、日向はもちろん、直射日光が当たらない明るい日陰でも栽培が可能です。