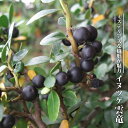モチノキ(イレックス)は属の中に約410種がありますが、一般に園芸で親しまれている種は幾つかの種とその園芸品種です。例えば、イヌツゲは刈り込みに強い事からトピアリーや生垣等に利用されます。またセイヨウヒイラギは柊を思わせる葉と冬に実る赤色の果実が特徴で実や葉のついた枝はクリスマス装飾に利用されたりします。その他にも長方形に棘のある葉が特徴的なヤバネヒイラギモチや、「苦労のない金持ち」という語呂合わせから縁起のよい植物として庭木等にして育てられるクロガネモチ等が親しまれています。
モチノキ(イレックス)属の種ごとの育て方は写真か育て方をクリックすると出てくる為よかったらそちらをご覧下さい!
このページでは主な種の種類と特徴、園芸品種の種類と特徴を紹介しています。
モチノキ(イレックス)の主な種の目次
イヌツゲの特徴や園芸品種


- 原産:日本/中国/朝鮮
- 学名:Ilex crenata
- 草丈:約200~1000cm
- 分類:常緑低木/常緑小高木
- 開花時期:6月~7月
- 花色:黄色●白色〇
- 葉色:緑色●黄色●白色〇
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 誕生花:1月10日/3月28日
- 花言葉:堅固/堅忍/淡白/冷静/禁欲主義
- 用途:カラーリーフ
イヌツゲとは!?
イヌツゲは学名Ilex crenata、別名では「ジャパニーズ・ホーリー(Japanese holly)」や「ボックス・リーブ・ホーリー(box-leaved holly)」とも呼ばれる日本および中国と朝鮮に自生する常緑低木もしくは常緑小高木です。
イヌツゲの語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のcrenataはラテン語で「鋸歯の形をした」や「刻み目のある」等を意味する「crenatus」の語尾変化で、葉の形に由来します。
- イヌツゲはツゲよりも成長が早く材の質が劣ると言われるため、本物と比べて「違う」や「役に立たない」を意味している「イヌ」がツゲの前についています。
イヌツゲの特徴(魅力)
- イヌツゲは、枝分かれがよくブッシュ状に密に茂る樹形と、緻密な印象を与える小さな葉が魅力の植物です。
- 園芸では、枝葉がブッシュ状に茂り、刈り込みに強く、葉が小さく緻密に仕上がる事から、トピアリー植物として人気が高く、また生垣や盆栽などにも利用されます。
 花は小さくクリーム色と目立たないため鑑賞目的で重要視される事はありません。
花は小さくクリーム色と目立たないため鑑賞目的で重要視される事はありません。- 花は蜜蜂の蜜源となるため、開花期になると花の周りを元気に飛び回る蜜蜂の姿や、花の中に頭を突っ込む蜜蜂の可愛らしい姿を観察する事が出来ます。
- 果実は食味が悪いため人間が食用として食べる事はほとんどないですが、ムクドリなどの鳥の食料源となっているため、果実を食べに来る鳥の姿を観察する事が出来るかもしれません。
- 葉は長さが約1~3cmととても小さく丸みを帯びており、葉のふち部分にギザギザとした小さな鋸歯がある所が特徴です。
- 葉の色はふつう緑色ですが、明るく開放的な印象を与える黄色の葉色などもあるため、品種を選んでカラーリーフとして楽しむ事も出来ます。
- イヌツゲは形状が整えられたフォーマルヘッジの生垣として利用されます。
- イヌツゲは葉が小さいため剪定をした時に形が綺麗に揃いやすく、また小さな葉のため途中で葉が剪断されても気になりません。表面を軽く剪定する事で枝葉が密に茂るため目隠し効果も高まります。
- イヌツゲを生垣として利用する場合の植付け間隔は約15~30cmです。
- イヌツゲは刈り込みに強く葉が小さいためトピアリー植物に向いています。
- トピアリーとしては球形に刈り込んだり、枠(フレーム)を利用して幾何学模様・動物・文字等の形等に剪定したりして形をつくります。
 イヌツゲは底の浅い鉢で仕立てられながら盆栽として育てられる事もあります。
イヌツゲは底の浅い鉢で仕立てられながら盆栽として育てられる事もあります。- イヌツゲとツゲは外観が似ている事から比較されることがあります。
- イヌツゲは雌雄異株のため雌株と雄株に分かれます。
- ツゲは雌雄同株のため1つの株に雌花と雄花があります。
- イヌツゲの花は6月から7月に開花します,
- ツゲの花は3月頃に開花します。
- イヌツゲの葉(葉序)は互生につきます。
- ツゲの葉は向かい合わせの対生につきます。
- イヌツゲの葉はふち部分にギザギザした鋸歯があります。
- ツゲの葉はふち部分が滑らかで全円です。
- イヌツゲの果実は丸く球形の核果で。
- ツゲは角張った蒴果を付けます。
- イヌツゲは雌雄異株のため雌株と雄株に分かれます。
- イヌツゲは夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
イヌツゲの樹高は約200(~1000)cm、樹形はブッシュ状で枝分かれがよく密に茂ります。樹皮は淡褐色もしくは灰色です。
葉序は互生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約1(~3)cm、幅約0.5(~1.7)cm、葉身の形は楕円形、葉のふち部分に鋸歯(稀に棘)があり、葉はしばしば隆起(凹凸)しています。
花序は雄株と雌株で変わり、雄株は散形花序に約2(~6)個の花が付き、雌株は腋花で単生します。雄株では、花弁が4個、花弁の色は白色もしくは黄色、雄蕊は4個あります。雌株では花弁が4個、花弁の色は白色もしくは黄色、雌蕊と不完全な雄蕊が4個あります。
果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果の色は黒色、形は球形、大きさは直径約0.6(~0.7)cmです。
イヌツゲの園芸品種の紹介
 ゴールデンジャム(ilex crenata ‘golden gem’)は、春に新しく成長する葉で見られる鮮やかな黄色の葉色と、成熟するにつれて見られるイエローグリーンの葉色が、カラーリーフとしてお庭の雰囲気を明るく爽やかに彩る魅力的な園芸品種です。高さ幅ともに約50~100cmに広がるため、背の低い生垣やトピアリーなどに向きます。
ゴールデンジャム(ilex crenata ‘golden gem’)は、春に新しく成長する葉で見られる鮮やかな黄色の葉色と、成熟するにつれて見られるイエローグリーンの葉色が、カラーリーフとしてお庭の雰囲気を明るく爽やかに彩る魅力的な園芸品種です。高さ幅ともに約50~100cmに広がるため、背の低い生垣やトピアリーなどに向きます。 スカイペンシル(ilex crenata ‘sky pencil’)は「鉛筆」を思わせる様な幅の狭い円柱形の樹形をつくる習慣(決まりのように繰り返す癖)をもつ園芸品種です。樹高は約150~300cm、横へは約50~100cmに広がります。スラリと真っ直ぐに成長する習慣から洗練されたお庭などによくあい、幅の狭い生垣や、庭の中で高さや立体感を出すアクセント植物としておすすめです。
スカイペンシル(ilex crenata ‘sky pencil’)は「鉛筆」を思わせる様な幅の狭い円柱形の樹形をつくる習慣(決まりのように繰り返す癖)をもつ園芸品種です。樹高は約150~300cm、横へは約50~100cmに広がります。スラリと真っ直ぐに成長する習慣から洗練されたお庭などによくあい、幅の狭い生垣や、庭の中で高さや立体感を出すアクセント植物としておすすめです。 ヒレリー(ilex crenata helleri)は、丸みを帯びるように成長する習慣(決まりのように繰り返す癖)があり、また枝葉が非常に密に茂ることから生垣やトピアリーなどに利用しやすい品種です。樹高は約60~120cm、横へは約100~150cmに広がり成長します。
ヒレリー(ilex crenata helleri)は、丸みを帯びるように成長する習慣(決まりのように繰り返す癖)があり、また枝葉が非常に密に茂ることから生垣やトピアリーなどに利用しやすい品種です。樹高は約60~120cm、横へは約100~150cmに広がり成長します。 キンメツゲ(ilex crenata ‘Kinnmetsuge’)は春の新芽が鮮やかな黄色もしくはクリーム色(薄黄色)をしているため、明るい雰囲気をつくるカラーリーフとして使える園芸品種です。基本的に殆ど雄株のため、果実はつかないと言われており、果実をつけない事から栄養の分散がないため樹勢が衰えにくいと言われています。樹高は約100~200cmまで成長します。用途に合わせて剪定しながら生垣やトピアリーなどに利用するとよいでしょう。
キンメツゲ(ilex crenata ‘Kinnmetsuge’)は春の新芽が鮮やかな黄色もしくはクリーム色(薄黄色)をしているため、明るい雰囲気をつくるカラーリーフとして使える園芸品種です。基本的に殆ど雄株のため、果実はつかないと言われており、果実をつけない事から栄養の分散がないため樹勢が衰えにくいと言われています。樹高は約100~200cmまで成長します。用途に合わせて剪定しながら生垣やトピアリーなどに利用するとよいでしょう。 マメツゲ(ilex crenata ‘convexa’)の特徴は葉の中央にある隆起(凹凸)で、英語の品種名Convexa(凸面)の由来にもなっています。また葉は小さく、濃い緑色で光沢があるため非常に美しく、剪定(刈り込み)に強いため生垣やトピアリー植物として重宝されています。樹高は約100~150cmまで成長します。
マメツゲ(ilex crenata ‘convexa’)の特徴は葉の中央にある隆起(凹凸)で、英語の品種名Convexa(凸面)の由来にもなっています。また葉は小さく、濃い緑色で光沢があるため非常に美しく、剪定(刈り込み)に強いため生垣やトピアリー植物として重宝されています。樹高は約100~150cmまで成長します。 雲竜は、は、枝が捻れてクネクネとした不規則な樹形をつくるため、樹形を楽しむ目的で庭木として楽しまれたり、盆栽として利用される事が多い園芸品種です。
雲竜は、は、枝が捻れてクネクネとした不規則な樹形をつくるため、樹形を楽しむ目的で庭木として楽しまれたり、盆栽として利用される事が多い園芸品種です。
| 楽天で購入 | |||
| | |||
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の特徴や園芸品種


- 原産:西・南ヨーロッパ/北西アフリカ/南西アジア
- 学名:Ilex aquifolium
- 草丈:約500~2500cm
- 分類:常緑高木
- 開花時期:4月~6月
- 果実時期:11月~12月
- 花色:白色〇
- 葉色:緑色●黄色●白色〇
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 誕生花:12月16日/12月25日
- 花言葉:慎重/洞察力/先見の明/不滅の輝き/将来の見通し/神を信じます
- 用途:カラーリーフ
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)とは!?
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)は学名Ilex aquifolium、別名では「セイヨウヒイラギモチ」や「ホーリー(holly)」とも呼ばれる西・南ヨーロッパおよび南西アジアと北西アフリカが原産の常緑高木です。
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のaquifoliumはラテン語で「棘のある葉」を意味しており、セイヨウヒイラギの葉のふち部分に刺がある事に由来します。
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の特徴(魅力)
- セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)は、ヒイラギと同様に葉のふち部分に鋭い棘があり、冬に赤色の果実をつける所が魅力の植物です。
- 園芸では冬に実る果実や装飾的な葉を鑑賞する目的で、庭木として育てられたり、鋭い葉が人や動物の侵入を阻む事から生垣として利用されたりしており、また枝葉と果実はクリスマス装飾の定番として利用されています。
- 樹皮の色は灰色、樹皮の上にはコルク質の目立つコブがある所が特徴です。
 花は葉腋から複数の白色の花が束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)しますが、小さく目立たないため鑑賞目的で重要視される事はありません。
花は葉腋から複数の白色の花が束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)しますが、小さく目立たないため鑑賞目的で重要視される事はありません。- 花は蜜蜂の蜜源となるため、開花期になると花の周りを元気に飛び回る蜜蜂の姿や、花の中に頭を突っ込む蜜蜂の可愛らしい姿を観察する事が出来ます。
 果実は赤く目立つ色をしており、葉腋に複数の果実が束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)して付きます。
果実は赤く目立つ色をしており、葉腋に複数の果実が束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)して付きます。- 果実はのクリスマス装飾の定番として利用されており、またフラワーアレンジメントなどにも利用されています。
- 果実は有毒(アルカロイド・サポニン等が含まれる)と考えられており食べる事は基本的に出来ませんが、間違えて摂取すると嘔吐(恐らくイリシンが原因)を誘発する事があります。
- 果実は実らせるには基本的に雄株と雌株の両方が必要ですが、稀に雌株の雌花の雄蕊が不稔性ではなく稔性の雄蕊をつける事があり、1本の株で結実することもあります。ただし、しっかり果実を楽しみたい場合は両方植えた方がよいでしょう。
- また1部品種では、自家受粉するものもあるため1本植えるだけで果実が楽しめる場合もあります。
 セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の生垣は樹形がある程度整ったフォーマルヘッジの生垣として利用されます。
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の生垣は樹形がある程度整ったフォーマルヘッジの生垣として利用されます。- セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)は葉に棘があるため人の侵入を阻む生垣としての働きがあり、また冬に実る赤色の果実を収穫してクリスマスの装飾に使ったり出来る所が魅力です。
- セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の生垣の植付け間隔は苗の大きさ等でも変わりますが約30cm~60cmです。
- セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)は、古代ケルト人の上位クラスのメンバーであるドイルドのお気に入りの木であり、神聖な木の1つとして扱われていました。
- またキリストの伝説では、ヘデロ王の兵士からイエスが逃れている時にセイヨウヒイラギが彼を兵士から保護したと言われており、またキリストの足元から初めて生えた植物と言われる事もあります。
- セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)は夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の樹高は約500(~2500)cm、幹の直径は約40(~100)cm、樹形はブッシュ状で枝分かれがよく密に茂ります。樹皮の色は灰色、樹皮の上にはコルク質のコブが出来る傾向にあります。
葉序は互生葉序、葉色は緑色、葉柄はあり、葉身の大きさは長さ約5(~12)cm、幅は約2(~6)cm、葉身の形は楕円形、葉の縁部分に歯牙(木が成熟すると歯牙がなくなり全円)と鋭い刺があり、葉の質感は革質で光沢があります。
花序は腋花、葉腋から複数の花が束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)しますが、雌株(雌花)は葉腋から1個のみ単生する事もあります。雄花は白色の花弁が4個と雄蕊が4個あります。雌花は白色の花弁が4個と雌蕊は1個と不稔性の雄蕊(稀に稔性の雄蕊)があります。
果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果の色は赤色もしくは黄色、形は球形、直径約0.6(~1)cmです。種子は果実に3(~4)個ふくまれます。
セイヨウヒイラギ(ヒイラギモチ)の園芸品種の紹介
 シルバークイーン(ilex aquifolium ‘silver queen’)は、葉のふち部分に入る白色(~薄黄色)の班と、新芽(~若葉)でしばしば見られる桃色に染まる可愛らしい葉色が魅力の園芸品種です。シルバークイーンは「クイーン(女王)」の名前をもちますが、雄株しかありません。そのため果実を実らせたい場合は他の品種も選択する必要があります。樹高は約400~800cmと背が高く成長するため十分なスペースをとって育てましょう。
シルバークイーン(ilex aquifolium ‘silver queen’)は、葉のふち部分に入る白色(~薄黄色)の班と、新芽(~若葉)でしばしば見られる桃色に染まる可愛らしい葉色が魅力の園芸品種です。シルバークイーンは「クイーン(女王)」の名前をもちますが、雄株しかありません。そのため果実を実らせたい場合は他の品種も選択する必要があります。樹高は約400~800cmと背が高く成長するため十分なスペースをとって育てましょう。 アラスカ(ilex aquifolium ‘alaska’)は自家受粉するため1本の木だけでも実が楽しめる園芸品種です。また一般的な種よりも葉の幅が狭く、光沢のある濃い緑色の葉色が美しく、密に枝葉が茂るため生垣としての利用が多いです。樹高は最大900cm、幅は600cmまで成長します。
アラスカ(ilex aquifolium ‘alaska’)は自家受粉するため1本の木だけでも実が楽しめる園芸品種です。また一般的な種よりも葉の幅が狭く、光沢のある濃い緑色の葉色が美しく、密に枝葉が茂るため生垣としての利用が多いです。樹高は最大900cm、幅は600cmまで成長します。 アルゲンテア・マルギナータ(ilex aquifolium ‘argentea marginata’)は葉のふち部分に入る白色(~薄黄色)の班と、晩秋~冬にかけて沢山実る赤色の果実がが魅力の園芸品種です。アルゲンテア・マルギナータは雌株しかありません。そのため果実を実らせたい場合は他の品種(雄株)も選択する必要があります。樹高は1200cmを越えて成長する可能性があるため十分なスペースをとって育てましょう。
アルゲンテア・マルギナータ(ilex aquifolium ‘argentea marginata’)は葉のふち部分に入る白色(~薄黄色)の班と、晩秋~冬にかけて沢山実る赤色の果実がが魅力の園芸品種です。アルゲンテア・マルギナータは雌株しかありません。そのため果実を実らせたい場合は他の品種(雄株)も選択する必要があります。樹高は1200cmを越えて成長する可能性があるため十分なスペースをとって育てましょう。 ジェーシーバントール(ilex aquifolium ‘jc van tol’)は、葉に棘がなく丸みを帯びた形状をした葉の形が特徴で、また自家結実性があるため1本の木があれば実をつける事が出来る園芸品種です。樹高は300~600cmを越えて成長する可能性があるため十分なスペースをとって育てましょう。
ジェーシーバントール(ilex aquifolium ‘jc van tol’)は、葉に棘がなく丸みを帯びた形状をした葉の形が特徴で、また自家結実性があるため1本の木があれば実をつける事が出来る園芸品種です。樹高は300~600cmを越えて成長する可能性があるため十分なスペースをとって育てましょう。
| 楽天で購入 | ||
| | ||
ヤバネヒイラギモチの特徴や園芸品種
- 原産:中国/朝鮮
- 学名:Ilex cornuta
- 草丈:約50~400cm
- 分類:常緑低木
- 開花時期:4月~6月
- 花色:白色〇
- 葉色:緑色●黄色●
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 用途:カラーリーフ
ヤバネヒイラギモチとは!?
ヤバネヒイラギモチは学名Ilex cornuta、別名では「シナヒイラギ」や「チャイニーズホーリー(Chinese holly)」とも呼ばれる中国および朝鮮が原産の常緑低木です。
ヤバネヒイラギモチの語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のcornutaはラテン語で「角のある」を意味します。
ヤバネヒイラギモチの特徴(魅力)
- ヤバネヒイラギモチは長方形に近い葉の形と、葉のふち部分に生える鋭い棘、秋から冬にかけて実る赤色の果実が魅力の植物です。
- 花は初夏頃に開花しますが小さく白色と目立たないため鑑賞目的として重要視される事はありません。
- 花は蜜蜂などの昆虫の蜜源として利用されます。
- 果実は花の少ない冬の時期に実るためウィンターガーデンを華やかに彩ります。
- 雌雄異株のため果実を実らせるのは雌株のみです。
- 果実を実らせるためには雄株と雌株の両方が必要になります。
- 葉は殆どが長方形をしておりふち部分に鋭い棘が3~7個あります。
- 葉色は光沢がある濃い緑色をしており幾つかの品種では葉の色が黄色(~白色)のためカラーリーフとして楽しまれます。
- ヤバネヒイラギモチは家の境界等に等間隔で植えて生垣として利用されます。
- 葉は常緑のため一年を通して鑑賞価値が保たれます。
- ヤバネヒイラギモチは底の浅い鉢で仕立てられながら盆栽として育てられる事もあります。
- ヤバネヒイラギモチは夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
ヤバネヒイラギモチの茎は木質で樹皮は灰褐色(~灰色)をしています。樹高は約50(~400)cm、樹形は円筒形、幹は直立にのびます。葉序は互生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約4(~9)cm、幅約2(~4)cm、葉身の形は楕円形で縁部分に歯牙と3(~7)個の鋭い刺があります。花は雌雄異株のため雄株(雄花だけ作る)と雌株(雌花だけ作る)がそれぞれ株が分かれてあります。果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、色は赤色、形は球形、直径約0.6(~1)cmです。種子は果実に3(~)個ふくまれます。
ヤバネヒイラギモチの園芸品種の紹介
モチノキの特徴や園芸品種
- 原産:日本/中国/台湾/朝鮮
- 学名:Ilex integra
- 草丈:約600~1000cm
- 分類:常緑小高木
- 開花時期:4月
- 花色:黄色●
- 葉色:緑色●
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 誕生花:12月19日
- 花言葉:時の流れ
- 用途:日陰植物/カラーリーフ
モチノキとは!?
モチノキは学名Ilex integra、別名では「ホンモチ」や「エレガンス・フィメール・ホーリー(elegance female holly)」とも呼ばれる日本および中国、台湾と朝鮮に自生する常緑高木です。日本では本州(東北以南)・四国・九州に分布して山地に自生しています。
モチノキの語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のintegraはラテン語で「完全な」を意味しています。
- モチノキの由来は、細かく砕いた樹皮を水につける事で不溶性の粘着物質を取り出す事が出来て、取り出した粘着物質を鳥黐(トリモチ)として利用したことからきています。
モチノキの特徴(魅力)
- モチノキは樹皮から小鳥や昆虫を捕獲する「鳥黐(トリモチ)」が取れる事からこの名前がついています。
- トリモチの作り方はモチノキの樹皮を細かく砕き、目の粗い袋に入れて流水の中に漬け2ヶ月から3ヶ月のあいだ水にさらします。水に数ヶ月さらすことで不要な木質部が腐敗し除去され、トリモチ成分だけが残ります。トリモチ成分を流水から取り出し、繊維質がなくなるまで砕きます。その後、流水で洗い残差を取り除きましょう。
- 花は小さくクリーム色と目立たないため鑑賞目的として重要視される事は殆どありません。
- 花は蜜蜂や昆虫の蜜源となるため開花期になると花の周りを元気に飛び回る蜜蜂や昆虫の姿が観察出来ます。
- モチノキの果実は1口サイズで食べやすいためヒヨドリやツグミなどがよく実を食べに来ます。そのためその鳥の姿を観察する事が出来ます。
- モチノキの葉は革質で濃い緑色をしており葉脈が殆ど見えないためのっぺりとした外観をしています。
- 葉色は通常は濃い緑色をしていますが幾つかの品種では葉の色が黄色のためカラーリーフとして楽しまれる事もあります。
- モチノキは家の境界等に等間隔で植えて生垣として利用されることがあります。
- 葉は常緑のため一年を通して鑑賞価値が保たれます。
- モチノキは雌雄異株のため雄株と雌株がありますが、しばしば性転換して雄株と雌株が入れ替わる事があります。
- モチノキは受粉しなくても果実を実らせる事が可能で、3割程は未受粉と言われています。
- モチノキは夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
モチノキの茎は木質で樹皮は灰褐色(~灰白色)をしています。樹高は約500(~1000)cm、樹形は円筒形です。葉序は互生葉序、葉色は濃い緑色で葉脈は殆ど見えず革質、葉身の大きさは長さ約4(~7)cm、幅約2(~3)cm、葉身の形は楕円形で、葉のふち部分は全円(稀に鋸歯)です。花は雌雄異株のため雄株(雄花だけ作る)と雌株(雌花だけ作る)がそれぞれ分かれてあります。雄花は2(~15)個の花が葉腋から束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)して、萼片が4個、花弁が4個、花弁の色は薄黄色、雄蕊は4(~6)個、雄蕊の色は黄色です。雌花は1(~4)個の花が葉腋から束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)して、萼片が4個と、花弁が4個、中央に子房と柱頭があり、周りに不稔性の退化した雄花が4個あります。果実は核果、色は赤色、形は球形、直径約1cmです。
モチノキの園芸品種の紹介
クロガネモチの特徴や園芸品種
- 原産:日本/中国/台湾/朝鮮
- 学名:Ilex rotunda
- 草丈:約500~2000cm
- 分類:常緑高木
- 開花時期:6月~7月
- 花色:黄色●紫色●緑色●
- 葉色:緑色●
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 誕生花:12月19日
- 花言葉:魅力/執着/寛容
- 用途:日陰植物
クロガネモチとは!?
クロガネモチは学名Ilex rotunda、別名では「クラシバ」や「クロガネ・ホーリー(Kurogane holly)」とも呼ばれる日本および中国、台湾と朝鮮に自生する常緑高木です。日本では本州・四国・九州に分布して山野に自生しています。
クロガネモチの語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のrotundaらラテン語で「円形」を意味します。
- クロガネモチ(黒金餅)の由来は葉が乾くと黒褐色になる所からきています。
クロガネモチの特徴(魅力)
- クロガネモチは、その名前から「苦労のない金持ち」という語呂合わせがされるため、縁起の良い樹木として扱われており、庭木や生垣などとして育てられている植物です。
- 花は小さくクリーム色と目立たないため鑑賞目的として重要視される事は殆どありません。
- 花は蜜蜂や昆虫の蜜源となるため開花期になると花の周りを元気に飛び回る蜜蜂や昆虫の姿が観察出来ます。
- クロガネモチの果実は1口サイズで食べやすいためヒヨドリやメジロなどがよく実を食べに来ます。そのためその鳥の姿を観察する事が出来ます。
- ただし食味が悪いため人間が食用として食べる事はほとんどありません。
- クロガネモチは家の境界等に等間隔で植えて生垣として利用されることがあります。
- 葉は常緑のため一年を通して鑑賞価値が保たれます。
- クロガネモチは雌雄異株のため雄株と雌株があり株によって果実が実らない株(雄株)があります。
- 雌株は雌花しか咲かせず中央に大きな子房と柱頭があり不稔性の退化した雄花が花弁の数だけあります。
- 雄株は雄花しか咲かせず花弁の数だけ薄紫色の雄蕊があります。
- クロガネモチは夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
クロガネモチの茎は木質で樹皮は灰褐色(~灰白色)をしています。樹高は約500(~1000)cm、樹形は円筒形です。葉序は互生葉序、葉色は緑色で光沢があり、葉身の大きさは長さ約4(~9)cm、幅約2(~4)cm、葉身の形は楕円形です。花序は散形花序、散形花序は花が2(~7)個つきます。花は雌雄異株のため雄株(雄花だけ作る)と雌株(雌花だけ作る)がそれぞれ分かれてあります。雄花は萼片が4(~6)個、花弁が4(~6)個、花弁の色は薄黄色(~薄緑色)、雄蕊は4(~6)個、雄蕊の色は淡紫色です。雌花は萼片が4(~6)個と、花弁が4(~6)個、中央に子房と柱頭があり、周りに不稔性の退化した雄花があります。果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、色は赤色、形は球形、直径約0.5(~0.8)cmです。
ソヨゴの特徴や園芸品種

- 原産:日本/中国/台湾
- 学名:Ilex pedunculosa
- 草丈:約300~700cm
- 分類:常緑小高木
- 開花時期:5月~7月
- 花色:白色〇
- 葉色:緑色●
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 誕生花:12月25日
- 花言葉:先見の明
- 用途:日陰植物/カラーリーフ
ソヨゴとは!?
ソヨゴは学名Ilex pedunculosa、別名では「ソヨギ」や「フクラシバ」とも呼ばれる日本および中国、台湾に自生する常緑小高木です。日本では本州(関東以西)・四国・九州に分布して山地に自生しています。
ソヨゴの語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のpedunculosaはラテン語で「花柄」を意味しており、ソヨゴの長い花柄に由来します。
- ソヨゴの由来は風に戦ぐ(そよぐ)と特徴的な音をさせる所からきています。
ソヨゴの特徴(魅力)
- ソヨゴは風で葉が揺れると「シャカ」「シャカ」と美しい音を響かせます。
- また葉を加熱すると内部で気化した水蒸気を溜め込んでしまうため、膨らみ音を立てて破裂するため「フクラシバ」の別名でも呼ばれています。
- ソヨゴは長い花柄(果柄)をもつ事から果実が実るとさくらんぼの様に垂れ下がる可愛らしい実を鑑賞出来ます。
- 果実は1口サイズで食べやすいためヒヨドリやメジロなどがよく実を食べに来ます。そのためその鳥の姿を観察する事が出来ます。
- ただし食味が悪く人間が食べる事は基本的にありません。
- ソヨゴは雌雄異株のため果実が実るのは雌株のみです。
- 花は小さくクリーム色と目立たないため鑑賞目的として重要視される事は殆どありません。
- 花は蜜蜂や昆虫の蜜源となるため開花期になると花の周りを元気に飛び回る蜜蜂や昆虫の姿が観察出来ます。
- ソヨゴの葉は革質で濃い緑色をしており葉のふち部分が曲線を描きながら波打ちます。
- ソヨゴは仕立て方により単幹(根元から上部まで幹が1本)になったり株立ち状(地際付近から幹・枝が立ち上がる茂る樹形)に育ったりします。
- 生垣として家の境界等に等間隔で植えて育てる場合は株立ち状に仕立てて育てると良いでしょう。
- シンボルツリーとして育てる場合は競合する幹や枝を剪定して取り除きながら育てるとよいでしょう。
- ソヨゴは夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
ソヨゴの茎は木質で樹皮は灰褐色(~灰色)をしています。樹高は約500(~700)cm、樹形は円筒形です。葉序は互生葉序、葉柄は約1(~2)cm、葉色は濃い緑色で葉脈は殆ど見えず革質、葉身の大きさは長さ約4(~8)cm、葉身の形は卵状楕円形で、葉のふち部分は全円で上下に波打ちます。花は雌雄異株のため雄株(雄花だけ作る)と雌株(雌花だけ作る)がそれぞれ分かれてあります。雄花は3(~8)個の花が葉腋から散形花序につき、萼片・花弁(白色)・雄蕊はそれぞれ4(~5)個あります。雌花は1(~3)個の花が葉腋から束生(葉・花・茎等が1箇所から束状に生える)して、萼片と花弁がそれぞら4(~5)個、中央に子房と柱頭があり、周りに不稔性の退化した雄花が4(~5)個あります。果実は核果、色は赤色、形は球形、直径約0.8cm、長さ約3(~4)cmの果柄にぶら下がりつきます。
ウメモドキの特徴や園芸品種
- 原産:日本
- 学名:Ilex serrata
- 草丈:約100~300cm
- 分類:落葉低木
- 開花時期:明朗/知恵/深い愛情
- 花色:桃色●白色〇
- 葉色:緑色●
- 耐暑性:強い
- 耐寒性:強い
- 誕生花:10月6日
- 花言葉:明朗/知恵/深い愛情
- 用途:日陰植物/カラーリーフ
ウメモドキとは!?
ウメモドキは学名Ilex serrata、別名では「ジャパニーズ・ウィンターベリー(Japanese winterberry)」とも呼ばれる日本原産の落葉低木です。日本では本州・四国・九州に分布して山地に自生しています。
ウメモドキの語源(由来)
- 属名のIlexの由来は、葉の類似性からセイヨウヒイラギガシ(Quercus ilex)が引用されたものです。
- 種小名のserrataは「鋸歯状」を意味しており、葉のふち部分がギザギザしている所からきています。
- ウメモドキの由来は葉の形が「うめ」に似ている所からきています。
ウメモドキの特徴(魅力)
- ウメモドキは花や実を楽しむ目的で庭木にしたり盆栽にする等して育てられ、また花や実を枝ものとして切り生け花などとして楽しまれます。
- ウメモドキの花は淡い桃色から白色をしており花の形 が「梅(ウメ)の花」に似ていると言われる事もあります。
- 花は雌雄異株のため雄花しか咲かない株と雌花しか咲かない株があります。
- 雄花は黄色の雄蕊が花弁の数だけあり、一つの葉腋から多数の花(雄花)が散形花序に集まり華やかに咲きます。
- 雌花は中央にみどりの子房と柱頭があり、一つの葉腋から1個もしくは2個から3個の花が集まり咲きます。
- 花は蜜蜂や昆虫の蜜源となるため開花期になると花の周りを元気に飛び回る蜜蜂や昆虫の姿が観察出来ます。
- ウメモドキの果実は秋から冬にかけて赤色に熟し実ります。
- 果実は落葉後も残るため花が少なくなるウィンターガーデンを明るく彩る事が出来ます。
- 果実は1口サイズで食べやすいためジョウビタキやメジロなどに好まれています。そのため果実が実る時期になると鳥の姿を観察する事が出来ます。
- ただし食味が悪く人間が食べる事は基本的にありません。
- ウメモドキは一般的に株立ち状(地際付近から幹・枝が立ち上がる茂る樹形)に成長しますが単幹(根元から上部まで幹が1本)に仕立てられる事もあります。
- ウメモドキは夏の暑さ冬の寒さに強いです。
- また地植えしている場合は水やりも肥料も殆ど不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。
ウメモドキの茎は木質で樹皮は灰褐色をしています。樹高は約100(~300)cm、樹形は一般的に株立ち状(地際付近から幹・枝が立ち上がる茂る樹形)です。葉序は互生葉序、葉色は緑色で、葉身の大きさは長さ約3(~8)cm、幅は約1.5(~3)cm、葉身の形は楕円形で、葉のふち部分は細かい鋸歯があります。花は雌雄異株のため雄株(雄花だけ作る)と雌株(雌花だけ作る)がそれぞれ分かれてあります。雄花は散形花序につき、萼片・花弁(白色もしくは桃色)・雄蕊はそれぞれ4(~5)個あります。雌花は1(~3)個の少数の花が集まり咲き、萼片と花弁(白色もしくは桃色)がそれぞれ4(~6)個、中央に子房と柱頭があり、周りに不稔性の退化した雄花が4(~6)個あります。果実は核果、色は赤色、形は球形です。
その他の種や園芸品種
- サニーフォスター(ilex × attenuata ‘sunny foster’)はダフンヒイラギ(Ilex cassine)とアメリカヒイラギ(Ilex opaca)の交雑種の園芸品種です。サニーフォスターは若葉が黄色の葉色になる事から、開放的で明るい印象を与えるカラーリーフとして楽しめる所が魅力です。また雌株と雄株があれば秋から冬にかけて真っ赤な果実が実るため、花の少なくなるウィンターガーデンを彩ってくれる所も魅力でしょう。樹形は円錐形、高さは約400cmまで成長します。
| 楽天で購入 | ||
| | ||